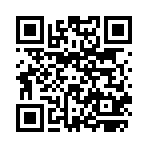2008年01月25日
第三十二夜 BAR 『CHARLIE BROWN』
~港町・BAR・アート(2)~

1950~60年代のロックンロールが身体に染み付いています。
プレスリー、モンキーズ、ビーチボーイズ、ビートルズ、ローリングストーンズなどなど・・・。
四人の男の子が高校を卒業し、それぞれの思いを胸に旅立っていくまでの一日の出来事を描いた「アメリカングラフィティ」は大好きな映画です。監督はスターウォーズなどのジョージ・ルーカス。リバイバルでしたが学生時代に何度もみました。
舞台は1962年、カリフォルニアの小さな町。
(記憶だけですが)主人公を演じたリチャード・ドレファスは、信号待ちで並んだ白いキャデラックの後部座席に乗っていた年上の女性と目が合います。そして「彼女は自分にほほえんだ」と思い込んで、一晩中探し回ります。挙句の果てはラジオ局に乗り込み、人気DJのウルフマン・ジャック(本物)にリクエスト曲とともに、キャデラックの彼女に「○○の電話ボックスに電話をかけてほしい」と放送してもらいます。時間はありません。翌日の飛行機で東部の大学に飛び立つわけですから・・・。
途中いろいろあって彼女が高級コールガールであることも聞かされます。
夜明け前、電話ボックス、じっとベルが鳴るのを待ちます・・・もうだめかと思いかけたその瞬間、ベルが鳴ります!!急いで受話器をとり「車ですれ違った僕を覚えてる?・・・・会いたい・・・」と告げます。彼女は「覚えている」・・そして・・・短いやりとりのあと電話は切られてしまいます。
翌日、彼は1人で東部へ旅立ちます。
飛行機の窓からそれまで過ごした町が見えます。
国道を白いキャデラックが走っています
彼の目にそれが入ったかどうか・・・・・エンディングの軽快なテンポのビーチボーイズ「終わりなき夏」が印象的です。
この映画には50年代~60年代のロックンロールがふんだんに使われていました。「ロックアラウンド・ザ・クロック」で始まり、ラストシーンの「終わりなき夏」まで懐かしいロックンロールであふれていました。
チェッカーズのヒット曲「涙のリクエスト」のイメージがなんとなく重なる映画です。

写真:ロックの名盤が「CHARLIE BROWN」の店内を飾る
場所は変わって2008年、KOBE・元町。
プレスリーのLPレコードが壁をぐるりと取り巻き、懐かしいロックンロールが流れているBARが元町海岸通にあります。BAR「CHARLIE BROWN」(チャーリー・ブラウン)というお店です。濃いブルーの名刺にALCOHOL & ROCK’N ROLLとあるように、とにかく感じのいいロックがかかっていて、一回行っただけですっかり気に入ってしまいました。元町の『MR酔っ払い』ヨシダ先生が「お前が好きそうな店を教えたる」と言って連れて行ってくれたBARです。
マスターの玉置さんも親切な方で、こんな曲ありますかと聞けば、合間にかけてくれたりします。
マスター曰く『このお店はデンマーク人のキディさんという方が1969年に始めたもので、当時元町に多くあった外人バーのひとつです。船乗りだったキディさんは天井を低めにして船室のような感じのお店にしたかったようです。壁も板壁で今では珍しいと思います。当時は外国人船員のお客も多く、お店に来ると入口近くに吊ってある鐘を鳴らして「来たよ」と合図していたらしいですよ』
実を言うと、外人バーは書き残しておきたいと思っていたテーマです。こんな言葉自体がもう特別な意味をもたないかもしれませんが、街の記憶が一杯詰まっている場所だと思っています。海を渡って異国の港町で根をおろされたキディさん。キディさんを慕ってやってきた多くの船員たち。港町が演出した「出合い」に蠢惑的な雰囲気を感じます。

写真:BAR「CHARLIE BROWN」への目印、青い看板
お店の場所はこの奥に店があるのか・・?と思うくらい細い路地、というよりもビルとビルの間の袋小路にあります。南京町の南門からさらにまっすぐ南へ、通りをふたつ越えたあたりです。捜してみてください。これ以上隠れ家的なバーはないかもしれませんよ!

1950~60年代のロックンロールが身体に染み付いています。
プレスリー、モンキーズ、ビーチボーイズ、ビートルズ、ローリングストーンズなどなど・・・。
四人の男の子が高校を卒業し、それぞれの思いを胸に旅立っていくまでの一日の出来事を描いた「アメリカングラフィティ」は大好きな映画です。監督はスターウォーズなどのジョージ・ルーカス。リバイバルでしたが学生時代に何度もみました。
舞台は1962年、カリフォルニアの小さな町。
(記憶だけですが)主人公を演じたリチャード・ドレファスは、信号待ちで並んだ白いキャデラックの後部座席に乗っていた年上の女性と目が合います。そして「彼女は自分にほほえんだ」と思い込んで、一晩中探し回ります。挙句の果てはラジオ局に乗り込み、人気DJのウルフマン・ジャック(本物)にリクエスト曲とともに、キャデラックの彼女に「○○の電話ボックスに電話をかけてほしい」と放送してもらいます。時間はありません。翌日の飛行機で東部の大学に飛び立つわけですから・・・。
途中いろいろあって彼女が高級コールガールであることも聞かされます。
夜明け前、電話ボックス、じっとベルが鳴るのを待ちます・・・もうだめかと思いかけたその瞬間、ベルが鳴ります!!急いで受話器をとり「車ですれ違った僕を覚えてる?・・・・会いたい・・・」と告げます。彼女は「覚えている」・・そして・・・短いやりとりのあと電話は切られてしまいます。
翌日、彼は1人で東部へ旅立ちます。
飛行機の窓からそれまで過ごした町が見えます。
国道を白いキャデラックが走っています
彼の目にそれが入ったかどうか・・・・・エンディングの軽快なテンポのビーチボーイズ「終わりなき夏」が印象的です。
この映画には50年代~60年代のロックンロールがふんだんに使われていました。「ロックアラウンド・ザ・クロック」で始まり、ラストシーンの「終わりなき夏」まで懐かしいロックンロールであふれていました。
チェッカーズのヒット曲「涙のリクエスト」のイメージがなんとなく重なる映画です。

写真:ロックの名盤が「CHARLIE BROWN」の店内を飾る
場所は変わって2008年、KOBE・元町。
プレスリーのLPレコードが壁をぐるりと取り巻き、懐かしいロックンロールが流れているBARが元町海岸通にあります。BAR「CHARLIE BROWN」(チャーリー・ブラウン)というお店です。濃いブルーの名刺にALCOHOL & ROCK’N ROLLとあるように、とにかく感じのいいロックがかかっていて、一回行っただけですっかり気に入ってしまいました。元町の『MR酔っ払い』ヨシダ先生が「お前が好きそうな店を教えたる」と言って連れて行ってくれたBARです。
マスターの玉置さんも親切な方で、こんな曲ありますかと聞けば、合間にかけてくれたりします。
マスター曰く『このお店はデンマーク人のキディさんという方が1969年に始めたもので、当時元町に多くあった外人バーのひとつです。船乗りだったキディさんは天井を低めにして船室のような感じのお店にしたかったようです。壁も板壁で今では珍しいと思います。当時は外国人船員のお客も多く、お店に来ると入口近くに吊ってある鐘を鳴らして「来たよ」と合図していたらしいですよ』
実を言うと、外人バーは書き残しておきたいと思っていたテーマです。こんな言葉自体がもう特別な意味をもたないかもしれませんが、街の記憶が一杯詰まっている場所だと思っています。海を渡って異国の港町で根をおろされたキディさん。キディさんを慕ってやってきた多くの船員たち。港町が演出した「出合い」に蠢惑的な雰囲気を感じます。

写真:BAR「CHARLIE BROWN」への目印、青い看板
お店の場所はこの奥に店があるのか・・?と思うくらい細い路地、というよりもビルとビルの間の袋小路にあります。南京町の南門からさらにまっすぐ南へ、通りをふたつ越えたあたりです。捜してみてください。これ以上隠れ家的なバーはないかもしれませんよ!
Posted by alterna at
18:41
│Comments(2)
2008年01月17日
第三十一夜 「進水式」

丹波の山奥の出身です。家のすぐ後ろが山でした。
40年くらい前のことですが、当時はまだ国産の木材がよく売り買いされていたようで、山師というのでしょうか、山々を渡って木を切り出す専門集団がいました。
あるとき山から流れ出ている小さな川(溝くらいなものです)の上に木の空中線路ができました。トラックが通れる位の道端から、ずっと山のなかにつづいています。
線路ができると男たちは山へ入り、木で組んだ船をつくり、その上に切り倒した木をたくさん積み込んで、木の線路の上をすべらせて、トラックのある道端まで運び出すという作業にとりかかりました。木を一杯に積んだ船はゆっくりと「とことこ」と静かな音をたてて進んでいました。山師たちは時々木の線路のメンテナンスをしていました。線路の上を歩きながら木船と線路の接点に油を塗っていくのです。なるほど油を敷いているからあんなに滑らかにすべるのか・・うまく考えたものだと子供心に感心した記憶があります。
線路は低いものでしたから、子供にとってはおもしろい遊具で、作業の休みの日には線路のうえを歩いてわたりました。ちょうど川の真上を空中散策するような感じです。

写真:4メートルくらいの碇
2008年1月14日午前11時過ぎ。神戸、川崎造船所内のドッグ。
大きな貨物船が海へと続く線路の上をゆっくりと音もなく滑っていき、歓声と拍手のなか見事に神戸港に浮かびました。線路の上には特殊な油が塗ってありました。
その日初めて知りましたが船の先端を「面(おもて)」といい、スクリュウのある後尾を「トモ」と言うらしく、パナマ船籍となった全長約190メートル、総トン数約31,000トンの巨大な貨物船は笛の合図とともに止め具を徐々に外されていき、3つ目の笛とともに最後の綱を船主の令嬢が切断すると、トモの方から港に浸かっていきました。船は進水させるときは必ずトモの方からするようです。

写真:港に向かって進む船
船の進水には「浸水式」と「すべり式」があるようで、浸水式は水を張るとともに、ドッグを沈ませるやり方で、すべり式は油を敷いたレールの上を滑らせて進水させるやり方と聞きました。浸水式がほとんどで、川崎造船の「すべり式」は大掛かりなものとしては日本でココだけのようです。油の敷き方も神戸の会社がもっている特殊技術のようです。この油のことを聞いて子供の頃の木の船のことを思い出していました。

写真:レールの油を取り除く作業
連れて行ってもらったグループ企業の川崎重工業の方(ジャズドラマーでもあります)に聞くと、『すべり式はもっとも原始的なやり方ですが、すべてが緻密に計算されています。全ての繋ぎをなくした船は敷かれた油のために、音もなくゆっくりと寸分たがわない軌道で港に向かっていきます。神戸港も狭くなりましたから、海に入ると船はゆっくりと右に旋回して止まりますよ。』
その方の言うとおりにすべてが進みました。一つ目の笛を聞いてから数分の出来事です。神戸市消防音楽隊のファンファーレが鳴り、クス玉がわれて風船と紙の吹流しが舞いました。
『「浸水係」という腕章は進水式で船を留めているクサビを外していく係りで、選ばれた少数の者にしか巻けないものです。この腕章は造船に関わっている者にとって誇りと栄光の象徴なのですよ』とも伺いました。

写真:進水して右に旋回
当日は数分のシーンをみるために2000人以上の人が詰め掛けたようです。そこここでかつてモノ造りに関わった人たちがあいさつを交わしていました。
「進水式は何度見ても感動する」という言葉を聞いて、一緒だった神戸製鋼所のOBの方も、『新しいプラントなどの火入れのときに「泣ける」のとよく似ている』と感慨深げでした。
船の名前は女性名が一般的らしく「SANTA THERESA」(サンタ テレサ)と命名された船は積荷もないことから、喫水線に余裕を残して冬晴れの神戸港に浮いていました。
Posted by alterna at
12:39
│Comments(0)