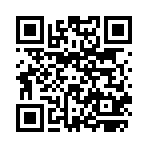2007年06月29日
第五夜:元町夜話・・南京町

写真:南京町西門
南京町は神戸でも元気な場所のひとつです。
確か日本で南京町という名称が今も使われているのは神戸だけのはずです。
長崎も横浜も中華街ですよね。
南京町では春節際や中秋節など季節ごとにいろいろな行事が行なわれます。
また伝統的なものだけでなく、中高生のジャズバンド部の子達を主役にした元町イーストジャズピクニックなどのイベントも企画実施されるなど人も町も元気です。
南京町は中華街ですから中華料理の店が多いのは当然ですが、案外に日本料理などの感じのいいお店も周辺に結構あります。
南京町の西門から入ってすぐの路地に「栗花落」という寿司屋さんがありました。
「つゆり」と読むようです。記憶が正しければ、これは苗字で、平安時代から続いているものだそうです。
20年くらい前に洋画家に連れて行ってもらいました。後にも先にもそれ一回なんですが・・・・というのは場所を覚えていなくて、次に捜しても分からなかった・・・中華街と感じのいい寿司屋とが奇妙な取り合わせのように思えて、その後もずっと覚えていました。
今年初め、場所がわかりましたが、看板だけになっていました。
そしてつい最近は看板もなくなって、新しいお店になっています。
そういえば6月の梅雨の頃に、栗の花が白く咲いては道に落ちていたのを思い出します。
栗の花は梅雨の頃に落ちる・・・だから「栗花落」で「つゆ・り(離?)」というのかな・・・などと当時は勝手に納得していて、いつまでも記憶に残っています。
五黄(ごおう)の寅(とら)(九星術で五黄土星の寅年生まれ・・・剛毅にして強運と言われる)だと自己紹介してくれたマスターも妙に懐かしいです。
なお、神戸市北区山田町には「栗花落の井」という井戸があるようです。
梅雨時になると水が湧き出し、秋になると止まるということらしいですが本当でしょうか?
身分違いの恋の成就と、悲しい別れの物語がこの井戸の水にまつわっているようです。
興味のある方はhttp://www.kobe-np.co.jp/rensai/p_water/28.htmlまで
Posted by alterna at
18:15
│Comments(0)
2007年06月22日
□楠公さん・・非理法権天
お店や場所に「さん」をつけて呼ぶのは一般的なんでしょうか?
コープさん、生田さん、楠公さん・・・などなど、神戸ではよく「さん」をつけるように思います。六甲山も「山」ではなく六甲「さん」なのかもしれません。
正確に呼ぶよりも親しみが込められていて、やわらかい感じがします。
楠公さん・・・湊川神社のことですが、楠正成公を祀っています。
湊川神社と楠正成公のことについては、神戸新聞の夕刊(火曜日)で連載されている一坂太郎さんの記述をとても興味深く読みました。
ところで、湊川神社の拝殿(一番奥の拝むところ)の天井絵をご覧になったことがありますか?
特に天井真ん中に据えられた龍の絵は迫力満点です。神戸ゆかりの日本画家福田眉仙先生の作です。眉仙・・中国は四川省にある急峻な名山「峨眉山」に住む「仙人」という意味だと聞いたことがあります。
湊川神社が天井絵の制作を東京在住の有名な日本画家に頼みにいったところ、「眉仙がおるではないか」と紹介されたことがきっかけになったらしいですが、本当でしょうか?
この眉仙画伯・・なかなか気骨のある人だったらしく、制作風景を撮影に来た新聞社のカメラマンが何気に作品を跨いだことに怒って、カメラを叩き落としました。後日そのカメラマンには「すまんことをした」と言って、一幅の絵を置いていったとか・・・。
いけばなの吉田泰巳先生に伺ったことですが、龍は中国では指を5本、朝鮮半島では4本、日本では3本で表現されることが多いようです。
よく見ると楠公さんの龍は3本の指で珠をしっかりとつかんで中空を睨んでいます。
まだの方は一度ご覧になってください。

なお、楠公さんは美術品の宝庫です。
版画家棟方志巧の大作が結構あります。
それと神社の境内にはりっぱな狛犬が5対鎮座しています。表神門をくぐって進むと鳥居の前に石彫(大正5年)のものが、社務所前の階段を上がると備前焼のもの、拝殿前に山崎朝雲作の金属製のもの、拝殿内に左右に配置された絵画が棟方志功作、そして拝殿奥にある木彫のものが平櫛(ひらぐし)田中(でんちゅう)の作と伺いました。見事5対捜せるでしょうか?
また、東京から移築された由緒ある能楽殿の松の絵は、見る人によっては「狸」が一匹見えるようです。僕には狸は笑っているように見えました・・・・。

コープさん、生田さん、楠公さん・・・などなど、神戸ではよく「さん」をつけるように思います。六甲山も「山」ではなく六甲「さん」なのかもしれません。
正確に呼ぶよりも親しみが込められていて、やわらかい感じがします。
楠公さん・・・湊川神社のことですが、楠正成公を祀っています。
湊川神社と楠正成公のことについては、神戸新聞の夕刊(火曜日)で連載されている一坂太郎さんの記述をとても興味深く読みました。
ところで、湊川神社の拝殿(一番奥の拝むところ)の天井絵をご覧になったことがありますか?
特に天井真ん中に据えられた龍の絵は迫力満点です。神戸ゆかりの日本画家福田眉仙先生の作です。眉仙・・中国は四川省にある急峻な名山「峨眉山」に住む「仙人」という意味だと聞いたことがあります。
湊川神社が天井絵の制作を東京在住の有名な日本画家に頼みにいったところ、「眉仙がおるではないか」と紹介されたことがきっかけになったらしいですが、本当でしょうか?
この眉仙画伯・・なかなか気骨のある人だったらしく、制作風景を撮影に来た新聞社のカメラマンが何気に作品を跨いだことに怒って、カメラを叩き落としました。後日そのカメラマンには「すまんことをした」と言って、一幅の絵を置いていったとか・・・。
いけばなの吉田泰巳先生に伺ったことですが、龍は中国では指を5本、朝鮮半島では4本、日本では3本で表現されることが多いようです。
よく見ると楠公さんの龍は3本の指で珠をしっかりとつかんで中空を睨んでいます。
まだの方は一度ご覧になってください。

なお、楠公さんは美術品の宝庫です。
版画家棟方志巧の大作が結構あります。
それと神社の境内にはりっぱな狛犬が5対鎮座しています。表神門をくぐって進むと鳥居の前に石彫(大正5年)のものが、社務所前の階段を上がると備前焼のもの、拝殿前に山崎朝雲作の金属製のもの、拝殿内に左右に配置された絵画が棟方志功作、そして拝殿奥にある木彫のものが平櫛(ひらぐし)田中(でんちゅう)の作と伺いました。見事5対捜せるでしょうか?
また、東京から移築された由緒ある能楽殿の松の絵は、見る人によっては「狸」が一匹見えるようです。僕には狸は笑っているように見えました・・・・。

Posted by alterna at
21:16
│Comments(0)
2007年06月22日
元町いまはむかし

写真
「大丸神戸店・・トアロード側」
シンガーソングライター増田俊郎さんの作品に「フェンスの向こうのアメリカ」という曲があり、
僕の学生時代だから・・・今から27・8年くらい前でしょうか?・・
柳ジョージ&レイニーウッドが歌ってました。名曲だと今も思っています。
その一節に「白いハローの子に追われて 逃げてきたPXから」という件りがあります。
終戦直後の横浜の米軍基地辺りが舞台だと思います。
PXとはアメリカ駐留軍(いわゆる進駐軍)専門のスーパーマーケットのことで、
敗戦国の日本の子供たちがものほしそうにガラス越しにPXの中を見ていると、ハローという言葉で
あいさつを交わす白い肌の子供たちが「ヤーイ、ヤーイ」と囃したてて追っかけてくる。
そんな情景がこの詞から浮かんできます。
神戸にもPXはありました。今の大丸神戸店の1階がそうだったようです。
これはおしゃれな彫刻家から聞いた話ですが、
『小学生の頃(終戦当時)、障子戸などの下についているローラーを打ち付けた板切れ
(スケートボードを想像してください)で、トアロードの坂を下っていくような遊びをしていた。
坂の終点には大丸があり、PXには色とりどりの包み紙にくるまれたチョコレートやキャンデーなどが
あふれるようにあった。』
ガラス越しにあったのは敗戦国日本ではなく、豊かで、おしゃれで、
眩しいくらいにかっこいいアメリカでした。
『PXの前には、シボレーやフォードなどの大きなオープンカーが止まっていて、袋一杯に買い物を
したアメリカ人の女性たちが進駐軍の将校と乗り込んで帰っていくのをよくみかけた。
「ヘイ!ボーイ」
運がよければ、そんな言葉とともに米兵がチューインガムやチョコレートを投げてくれた。
そりゃ戦争に負けるわ』・・と。
戦前戦後を通じて、神戸の大丸周辺は時代の変化に向かい合う最先端の「場所」でした。
内側に異国(異文化、多様性)をもつ街には個性的な文化が育ちます。戦前には内なる西洋、
戦後では内なるアメリカをもっていた神戸には異国情緒、モダニズムといった
今の街のもつイメージが形成されていきました。そして多くのアーティストが活躍しました。
(これを書き始めると長くなるので、このつづきはまたの機会に)
Posted by alterna at
21:14
│Comments(0)
2007年06月22日
元町界隈(7月までだ!hurry up!)
元町には時代感のあるビルヂングが多くあります。もともと個性的なお店が多いですが、
ここ数年来、若い感性が入り、今を映す雰囲気のあるお店がまた新しい個性を生み出しています。
個人的な好みながら、大丸側から元町商店街に入ってすぐ左の路地に『CUBE』というバーが
あるのをご存知でしょうか?

古いドアを開けると、暗い階段があって、2階と3階がバーになっています。
客層は若い男女が多く、ときどき僕のようなやや場違いなおっさんが来ています。
さらに輪をかけたおっさん(名前は言えません)が階段からすべり落ちて肋骨を折ったりもします。
そのことがあってから階段には手すりがつきました。
カウンターでは八百屋さんもやっている異色のオーダーIidaさんやSyoutaさん、Kenさん、そして謎の若い衆といった個性的なバーテンダーが迎えてくれます。メキシカンな雰囲気を狙ったという黄色味がかった店内は気取らない感じでなかなかGOODです。

背の高い方が、オーナーのIidaさん その隣りが謎の若い衆
でもこの店、4月で3階を閉めました。2階も7月までの営業です。
経営がしんどいのかというとそうでもないようなんです。みんなそれぞれにやりたいことができたのが理由のようです。でも店の雰囲気を築いてきた仲間以外には継いで欲しくない・・・・・だから閉めようと。
もったいないし寂しい気もしますが、そういうのもいいかなと今は思っています。遠くない将来、元町のバー伝説の一つになるかもしれません。
7月まで!と書きましたが、7月に入るとやってないのか、7月31日までやっているのか、はっきりと覚えていません(酔っ払いは大事なことから忘れます)。
興味のある方はお早めに。
Hurry up
ここ数年来、若い感性が入り、今を映す雰囲気のあるお店がまた新しい個性を生み出しています。
個人的な好みながら、大丸側から元町商店街に入ってすぐ左の路地に『CUBE』というバーが
あるのをご存知でしょうか?

古いドアを開けると、暗い階段があって、2階と3階がバーになっています。
客層は若い男女が多く、ときどき僕のようなやや場違いなおっさんが来ています。
さらに輪をかけたおっさん(名前は言えません)が階段からすべり落ちて肋骨を折ったりもします。
そのことがあってから階段には手すりがつきました。
カウンターでは八百屋さんもやっている異色のオーダーIidaさんやSyoutaさん、Kenさん、そして謎の若い衆といった個性的なバーテンダーが迎えてくれます。メキシカンな雰囲気を狙ったという黄色味がかった店内は気取らない感じでなかなかGOODです。

背の高い方が、オーナーのIidaさん その隣りが謎の若い衆
でもこの店、4月で3階を閉めました。2階も7月までの営業です。
経営がしんどいのかというとそうでもないようなんです。みんなそれぞれにやりたいことができたのが理由のようです。でも店の雰囲気を築いてきた仲間以外には継いで欲しくない・・・・・だから閉めようと。
もったいないし寂しい気もしますが、そういうのもいいかなと今は思っています。遠くない将来、元町のバー伝説の一つになるかもしれません。
7月まで!と書きましたが、7月に入るとやってないのか、7月31日までやっているのか、はっきりと覚えていません(酔っ払いは大事なことから忘れます)。
興味のある方はお早めに。
Hurry up
Posted by alterna at
21:09
│Comments(0)
2007年06月22日
KOBE千話一夜物語 ~人と街への尊敬を込めて~
人もすなるブログなるものを書くことになりました。
出来心です。
KOBE 千話一夜物語と名付けました。千夜一夜だと夜が2回続くので、千話としました。
いろいろな話を一夜話として紹介するという・・・ただそれだけで大した意味はありません。
僕は神戸出身ではありません。兵庫県の北の方で、子供の頃、山の向こうの南の方にあこがれを持っていたものです。
縁あって神戸で働いています。
そして幸運にも「自分の神戸」を持っている多くの人と出会いました。
僕のような者には自分の神戸を持っている人たちが話すいろいろなことが面白くてしかたありません。
そこで今回「・・・のようです。」というような伝聞言葉を多用しますが、ご紹介したいと思います。
照れ屋なので名前は匿名の「僕」にします。
いろいろと書きますが、時代考証などはしていません。ただ、人と街への尊敬を込めて書いていきます。
出来心です。
KOBE 千話一夜物語と名付けました。千夜一夜だと夜が2回続くので、千話としました。
いろいろな話を一夜話として紹介するという・・・ただそれだけで大した意味はありません。
僕は神戸出身ではありません。兵庫県の北の方で、子供の頃、山の向こうの南の方にあこがれを持っていたものです。
縁あって神戸で働いています。
そして幸運にも「自分の神戸」を持っている多くの人と出会いました。
僕のような者には自分の神戸を持っている人たちが話すいろいろなことが面白くてしかたありません。
そこで今回「・・・のようです。」というような伝聞言葉を多用しますが、ご紹介したいと思います。
照れ屋なので名前は匿名の「僕」にします。
いろいろと書きますが、時代考証などはしていません。ただ、人と街への尊敬を込めて書いていきます。
Posted by alterna at
21:00
│Comments(0)