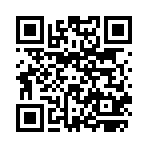2008年10月28日
第五十夜 神戸の音文化(その1)
日本でトップのジャズ喫茶といったら多くの人が岩手県一関市の「ベイシー」をあげられると思います。観光地図にも表示されているようですから、相当多くの人が訪ねるのだと思います。日本でトップかどうかよりも自分が一番心地よく居られるお店が一番いいわけですが、この「ベイシー」は半端ではないようで、ジャズフアンやオーディオフアンには一目置かれているようです。
「東京からここ(岩手)まで人を呼んでみせる」という思いでマスターは始められたと随分と昔に人づてに聞いたことがあります。
行ったことはありませんが、また行ったとしても僕の耳ではそこまで理解できるとも思いませんが、とにかくなかなか極めたお店には違いないと思います。
神戸にも「音」を極めたようなお店があります。
(個人的には20年ほど前に阪急三ノ宮駅の山側にあった、「バンビ」というレコード喫茶がわけあって懐かしいのですが、今はもうありません)

写真:「ジャスト・イン・タイム」 ブロンズのミュージシャン
♪ジャズ喫茶「ジャスト・イン・タイム」
1958年頃から1980年代にかけて手作り生産されていた名スピーカー「JBLパラゴン」がうなりをあげて迫ってきます(ちなみにこのスピーカーの最後の職人は日系の方・・・日本人ともききました・・のようです)。
お店のコンセプトとして、雰囲気・コーヒーの味・音など全ての要素を80パーセント以上にしたいという磯田マスターのこだわりの空間です。
「このパラゴンの能力の80%は引き出せていると思う」・・・マスターの静かな自信が分厚いベース音とともに硬い床を伝わってきます。コーヒー、ココアがお勧めです。最近「紅茶は入れ方が難しいけど、ようやくわかった!」というマスターの独り言をききました。お試しください。
お店の調度類もお洒落で、ちょっとしたものがいい雰囲気を醸しています。

写真:JBLパラゴン

写真:棚に置かれたジャズの人形
ジャスト・イン・タイムは音の宝庫ですが、同時に人の宝庫でもあります。ここで出会った多くの人たちに神戸らしいお店やエピソードをいろいろと教えてもらいました。このブログの多くはここ発のものも多くあります。色々なお店を見ていて思うのは、マスターとお客の会話や関わりのなかからお店の雰囲気なりが形成されていくということです。それは街の雰囲気やイメージが色々な人が集まり刺激しあうなかから形成されていくことに似ているように思います。人の求心力のある磁場のような場所が一杯ある街には豊かな文化が創られていくということを感じます。

写真:西村功さんの版画
なお、ジャスト・イン・タイムは凛としたジャズのお店です。この神聖なジャズの場所を先日ハードロックで汚してしまいました。元町高架下の中古レコード屋でハードロックの王者「DEEP PURPLE」のレコード「イン・ザ・ロック」を見つけて買ってしまいました。ジャスト・イン・タイムにふらっと立ち寄ったところ、お客はロックからジャズまで柔軟に聞ける人たちばかりが二人、そしてマスター・・・みんな知り合いです・・・「チャンス!!!」・・・と哀願した上目遣いでマスターを見ると何故か「かけてみよか?」「そんな・・聖地を汚すなんて・・・いいんですか・・」
と雰囲気は傾いて行きまして、ジャズの静かな聖域は一転してガンガンのロックの鳴り響く空間になりました。
30年以上も前のロックですが、改めてディープ・パープルは凄いと思いました!!!マスターありがとうございました!!!
お店は元町通3丁目13-1(元町商店街を西へ、海文堂書店の角を山側へすぐ)
URL http://www.sound.jp/justintime
・・・50回目を迎えて
このブログを書き初めて1年と半年くらいが過ぎました。正直なところこのマイナーネタでよく続いたと思います(勝手に書いてきただけなのですが・・)。
『神戸千話一夜物語』というタイトルはアラビアンナイトの『千夜一夜物語』から借用しています。最初は変化をつけず『神戸千夜一夜物語』にする予定でしたが、「元町のMR酔っ払い」として再々登場する吉田先生に相談したところ、「もう一ひねりした方がおもしろいぞ」と言われて、少し考え、多くの人に聞いた色々な話し、エピソードを神戸らしいお店の紹介と絡めていますので「千夜」ではなく『千話』、これを一回完結型で一夜(いちや)語りすることと、物語はやはり人の世の出来事なので、読み方を「一夜(いちや)」ではなく「一夜≒人世(ひとよ)」として『神戸千話一夜物語』(こうべせんわひとよものがたり)としました。
紹介しているエピソードには聞き伝えも多くて、実際がどうだったかわからないものもあるのですが、あえて勘違いは勘違いのまま、半分は物語でいこうということにしました。その意味でこのブログの中身は「現実」や「事実」ではなく「幻」と「実」・・・「幻実」です。
続けていくなかで貴重なメッセージを寄せていただいたこともあり素直に喜んでいます。
先日などはこのブログを見てお店に来ましたという22歳の社会人1年生の人と偶然出会いました。色々なアンテナをもつと、人も歩けば人に当たる(?)という偶然が縁を結んでくれるという実感がしています。
いい経験をさせていただいたKO-COさんに感謝します。
ありがとうございました
「東京からここ(岩手)まで人を呼んでみせる」という思いでマスターは始められたと随分と昔に人づてに聞いたことがあります。
行ったことはありませんが、また行ったとしても僕の耳ではそこまで理解できるとも思いませんが、とにかくなかなか極めたお店には違いないと思います。
神戸にも「音」を極めたようなお店があります。
(個人的には20年ほど前に阪急三ノ宮駅の山側にあった、「バンビ」というレコード喫茶がわけあって懐かしいのですが、今はもうありません)
写真:「ジャスト・イン・タイム」 ブロンズのミュージシャン
♪ジャズ喫茶「ジャスト・イン・タイム」
1958年頃から1980年代にかけて手作り生産されていた名スピーカー「JBLパラゴン」がうなりをあげて迫ってきます(ちなみにこのスピーカーの最後の職人は日系の方・・・日本人ともききました・・のようです)。
お店のコンセプトとして、雰囲気・コーヒーの味・音など全ての要素を80パーセント以上にしたいという磯田マスターのこだわりの空間です。
「このパラゴンの能力の80%は引き出せていると思う」・・・マスターの静かな自信が分厚いベース音とともに硬い床を伝わってきます。コーヒー、ココアがお勧めです。最近「紅茶は入れ方が難しいけど、ようやくわかった!」というマスターの独り言をききました。お試しください。
お店の調度類もお洒落で、ちょっとしたものがいい雰囲気を醸しています。
写真:JBLパラゴン
写真:棚に置かれたジャズの人形
ジャスト・イン・タイムは音の宝庫ですが、同時に人の宝庫でもあります。ここで出会った多くの人たちに神戸らしいお店やエピソードをいろいろと教えてもらいました。このブログの多くはここ発のものも多くあります。色々なお店を見ていて思うのは、マスターとお客の会話や関わりのなかからお店の雰囲気なりが形成されていくということです。それは街の雰囲気やイメージが色々な人が集まり刺激しあうなかから形成されていくことに似ているように思います。人の求心力のある磁場のような場所が一杯ある街には豊かな文化が創られていくということを感じます。
写真:西村功さんの版画
なお、ジャスト・イン・タイムは凛としたジャズのお店です。この神聖なジャズの場所を先日ハードロックで汚してしまいました。元町高架下の中古レコード屋でハードロックの王者「DEEP PURPLE」のレコード「イン・ザ・ロック」を見つけて買ってしまいました。ジャスト・イン・タイムにふらっと立ち寄ったところ、お客はロックからジャズまで柔軟に聞ける人たちばかりが二人、そしてマスター・・・みんな知り合いです・・・「チャンス!!!」・・・と哀願した上目遣いでマスターを見ると何故か「かけてみよか?」「そんな・・聖地を汚すなんて・・・いいんですか・・」
と雰囲気は傾いて行きまして、ジャズの静かな聖域は一転してガンガンのロックの鳴り響く空間になりました。
30年以上も前のロックですが、改めてディープ・パープルは凄いと思いました!!!マスターありがとうございました!!!
お店は元町通3丁目13-1(元町商店街を西へ、海文堂書店の角を山側へすぐ)
URL http://www.sound.jp/justintime
・・・50回目を迎えて
このブログを書き初めて1年と半年くらいが過ぎました。正直なところこのマイナーネタでよく続いたと思います(勝手に書いてきただけなのですが・・)。
『神戸千話一夜物語』というタイトルはアラビアンナイトの『千夜一夜物語』から借用しています。最初は変化をつけず『神戸千夜一夜物語』にする予定でしたが、「元町のMR酔っ払い」として再々登場する吉田先生に相談したところ、「もう一ひねりした方がおもしろいぞ」と言われて、少し考え、多くの人に聞いた色々な話し、エピソードを神戸らしいお店の紹介と絡めていますので「千夜」ではなく『千話』、これを一回完結型で一夜(いちや)語りすることと、物語はやはり人の世の出来事なので、読み方を「一夜(いちや)」ではなく「一夜≒人世(ひとよ)」として『神戸千話一夜物語』(こうべせんわひとよものがたり)としました。
紹介しているエピソードには聞き伝えも多くて、実際がどうだったかわからないものもあるのですが、あえて勘違いは勘違いのまま、半分は物語でいこうということにしました。その意味でこのブログの中身は「現実」や「事実」ではなく「幻」と「実」・・・「幻実」です。
続けていくなかで貴重なメッセージを寄せていただいたこともあり素直に喜んでいます。
先日などはこのブログを見てお店に来ましたという22歳の社会人1年生の人と偶然出会いました。色々なアンテナをもつと、人も歩けば人に当たる(?)という偶然が縁を結んでくれるという実感がしています。
いい経験をさせていただいたKO-COさんに感謝します。
ありがとうございました
Posted by alterna at
09:39
│Comments(18)
2008年10月10日
第四十九夜 名トランペッター右近雅夫さんにブラボー!!!
今年(2008年)は第1回のブラジル移民の人たちが、1908年4月28日に神戸港を出発し、6月18日にブラジルサントス港に到着してから100年目に当たります。ブラジルには世界最大の日系人コロニーが形成されており、その数140万人とも150万人とも言われています。近年は6世の子が生まれるまでになったようですが、ここまでにいたる道のりは決して平坦なものではなかったようです。
神戸港は約25万人の人たちがブラジルを中心とした南米に旅立った港です。移住のために日本全国から集まった人たちが出港までの10日あまりを過ごし、移住先の文化や言葉などを習得した場所が鯉川筋を登りきったところにある「旧神戸移住センター」です。センターは1928年に開設、1971年に閉鎖され、その後は色々な使われ方をされましたが、現在耐震補強のための改修工事が進められています。ここから旅立った日系ブラジル人の人たちにとって、センターはまさに「懐かしい我が家」のような場所でしょうし、神戸の港文化を象徴する場所でもあると思います。
ガリンペイロ(Garimpeiro)・・・ポルトガル語で「砂金採り」を意味するそうです。ポルトガル語が公用語のブラジルでは一攫千金の夢を追いかけて山や谷に入り、宝石を掘り当てたり、砂金を採ったりする人たちのことを指す言葉のようです。
こんなエピソードを聞きました。
日本からブラジルに移住した家族が離散し、幼い兄弟二人が路頭に投げ出されました。二人はコインを投げ、道路の右と左のどちらを歩くかを決め、二度と出会うことは無いという覚悟で、それぞれの道(未知)を歩くことにしました。結果として一人の子はカードゲームの世界で名をはせる世紀の賭博師になり、もう一方の子は(歯)医者となって、二人とも自分の人生をつかみとり、行き倒れにはなりませんでした。生き抜くために前に向かって歩いていったこの二人のエピソードに、僕はどうしてもガリンペイロという言葉が重なります。「人間の強さ」と「運」を物語るエピソードだと思います。
因みに西部開拓史の頃、カリフォルニアで金が見つかってゴールドラッシュが起こりますが、この頃砂金採りが歌ったのが「愛しのクレメンタイン」です。このクレメンタインは実在の女性のことではなく、砂金という「愛しい存在」のことだったとも聞いたことがあります。
ただ、OK牧場の決闘を描いた西部劇「荒野の決闘」では、クレメンタインは美しい女性教師として出てきます。ヘンリー・フォンダが演じた名保安官ワイアット・アープは、「好きです」という言葉が言えず、「クレメンタイン・・・本当にいい名前ですね(または「クレメンタインという名前が大好きです」という字幕もありました)」というセリフを残して去っていくラストシーンは名場面だと思います。

写真:北の坂にあるジャズストリートのプレート
1955年(昭和30年)。神戸出身の伝説の名トランペッターが神戸港からブラジルに渡りました。その人の名前は右近雅夫さん。
昭和28年に神戸にきていたジャズの巨人ルイ・アームストロングは、二十歳そこそこの日本人の若者が吹き込んだレコードを聴き、しかもその奏者が目の前にいる右近青年と知ったとたん「OH MY BOY!!」と言って抱き寄せたというエピソードが神戸ジャズストリートのホームページで紹介されています。右近さんは関西学院出身で、「デキシーランド・ハートウォーマーズ」というジャズバンドの基礎を作り、昭和20年代に神戸を中心に活躍されました。神戸はデキシーランドジャズ(デキシーランドはアメリカ南部を指す言葉)のメッカとも言われるようですが、デキシーランド・ハートウォーマーズと右近さんの存在が大きく影響しているようです。
その右近さんが10月4・5日に行なわれた神戸ジャズストリートに出演されていました。自身3回目のジャズストリート参加ですが、ブラジル移住100周年に演奏されるのもなにかしら縁を感じます。日本を離れて半世紀以上、今は実業家として成功されていますが、どんなときもトランペットは一緒だったと話されていました。
写真:演奏する右近雅夫さん(中央)
「未知の大陸に多くの日本人が夢を追いかけたと思いますが、成功と失敗を分けたのは何だったと思われますか?」という問いに、
「くよくよ考えずになんとかなると常に楽観的な心をもつこと」と答えてくださいました。雰囲気も目元のしわも演奏される音楽と同じで、優しく、包み込むような豊かさを感じる人でした。
歴史の偶然は50年以上も前の物語りを僕に披露してくれました。右近さんの歩まれた人生はあまりに「自然体」そのものという印象をうけました。
「50年以上日本を離れてるけど、関西弁だけは忘れてまへん」ユーモアたっぷりにステージで話され、久しぶりの神戸とジャズを自身楽しまれていました。
右近雅夫さんいつまでもお元気で!!!
Posted by alterna at
11:13
│Comments(0)