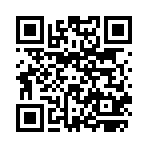2007年07月27日
第九夜 神戸の洋食屋さん

写真:伊藤グリル
神戸は明治の開港以来、みなとを軸に「ひと」「もの」「こと」に関する世界と日本の窓口となって「文化の翻訳と伝達」という歴史を築き上げてきました。ジャズ、映画、洋菓子、ゴルフ、コーヒ、パーマネント、洋家具など「神戸はじめ」と呼称される数々のものは、神戸がいちはやく世界の文化を取り入れ、全国に発信する街だったことの証しです。
実は「洋食屋さん」も神戸らしさを伝える街の魅力だと思っています。
鎖国が解かれた日本。富を求めて次々にやってくる欧米列強国の商人たち。
造船など新しい産業で賑わう街を支えた人たち・・・。
その活動を支え、疲れを癒す料理を提供したのは客船やホテルなどのコックたちでした。真摯に学び、外国人客の細かなオーダーに応じる過程で鍛えられ、そしてさらなる研究を重ねて味を探求したコックたちの、好奇心と職人気質が神戸洋食のルーツを形成していきます。
神戸洋食の系譜は、1882年に旧居留地に開業したオリエンタルホテルなどで修行し、独立していったコックたちの系統(その他のホテルの系統も含みます)。もうひとつは豪華客船で欧米と神戸を結んだ「日本郵船」で船旅を支えたコックたちが陸にあがって開いた洋食屋の系統。そしてもうひとつは、かつて「東の浅草、西の新開地」と呼ばれた文化の情報発信拠点だった街・新開地で生まれ東へ向かった洋食の系統です。

写真:左から ハナワグリル、グリル一平、帝武陣
神戸洋食の三つの系譜にルーツをもつコックたちが、港まち神戸で洋食屋として伝統のなかにも個性あるその店ならではの「味」を今日まで伝えています。それは「味」を毎日一から作るのではなく、伝統の「味」のベースやレシピを受け継ぎ、素材を継ぎ足し継ぎ足しすること、つまり元の味に近づけようとする模索のなかで独自の味が創られていったのです。神戸洋食の伝統の「味」はただ守られているのではありません。そこには常に創意と工夫が加えられ、「進化し続ける伝統の味」というべきものが、ノスタルジックな暖簾のむこうに、今日もその店のアラカルトなどを通して提供されています。
今、ご当地検定など、さまざまな分野で「らしさ」と言うものを再認識しようという試みがされています。神戸が街の個性を都市ブランドとして発信し、多くの方に神戸の魅力を知ってもらうためには、神戸「らしさ」を再認識する努力を怠ってはならないと思います。伝統と現代が融合された神戸洋食は神戸らしさの一角を担う都市ブランドのひとつだと思います。
ex:日本郵船系:伊藤グリル、ハイウエイ、明治屋神戸中央亭など
旧オリエンタルホテル系:クックナカタ、神戸開花亭、帝武陣など
その他ホテル系:神戸キチン、十字屋、ハナワグリル、もんなど
新開地発祥:赤ちゃん、グリル一平など
注:独断的分類ですので、詳しくはお店などで確認してください
Posted by alterna at
18:05
│Comments(0)
2007年07月24日
第八夜 55.5°
この数字は何だと思いますか?
地球上で確認された最高気温のことではありません。
すぐにわかった方は相当にマニアックな方です。敬意を込めて「達人」の称号を贈りたいと思います。

写真:三宮にあった頃の55.5°
これは神戸市内にあった彫刻の名前です。
場所は現在建設工事が進んでいる三宮の播州信用金庫神戸本部の西側で三宮中央通駐車場出入口付近(以前あった東京銀行神戸支店前広場)だったと思います。
作者は山口牧生さん。
大阪は能勢の石切り場で産出する石と向かい合った作家です。
環境造形Qというグループ(小林陸一郎、増田正和、山口牧生)で活躍もされました。Qの仕事としてはメリケンパークの映画の碑、ポートアイランド北公園のイルカの作品などがあります。
実は神戸市は彫刻の街として有名です。市内には450を超える野外彫刻があります。「55.5°」もそのひとつで、竜の舌のような赤黒い能勢石(黒御影石)が55.5°の角度で南方上空に向かって突き出ていました。
この作品・・・この角度に意味があります。
春分と秋分の日の年2回、南中した太陽の高度とピタリと合わさり、作品の影がなくなるのです。1年に2回だけ無言で時を告げる日時計なのです。
地球と太陽の位置からくる自然のリズムと日本という場所に住む私たちの生活のリズムが、力のある作家のひらめきと技術によって芸術作品に凝集されています。
残念ながら作品は阪神大震災の頃に三宮からなくなりました。
山口先生も今は鬼籍の人です。
でも作品の記憶はいつまでも残像として残っています。
元町画廊には山口先生の作品が数点展示してあったと思います。
なお、その後「55.5度」は移転されていたことが分かりました。
今回何気に検索してみると、垂水区にあるベルデ名谷1番館南西側にあることがわかりました。
懐かしい人に出会った気分です。
以下のホームページで神戸の野外彫刻を紹介されている方がいます。
非常に労力のかかる作業だと思います。
http://www.rokko.gr.jp/~icchan2/7taru/7210.htm
地球上で確認された最高気温のことではありません。
すぐにわかった方は相当にマニアックな方です。敬意を込めて「達人」の称号を贈りたいと思います。

写真:三宮にあった頃の55.5°
これは神戸市内にあった彫刻の名前です。
場所は現在建設工事が進んでいる三宮の播州信用金庫神戸本部の西側で三宮中央通駐車場出入口付近(以前あった東京銀行神戸支店前広場)だったと思います。
作者は山口牧生さん。
大阪は能勢の石切り場で産出する石と向かい合った作家です。
環境造形Qというグループ(小林陸一郎、増田正和、山口牧生)で活躍もされました。Qの仕事としてはメリケンパークの映画の碑、ポートアイランド北公園のイルカの作品などがあります。
実は神戸市は彫刻の街として有名です。市内には450を超える野外彫刻があります。「55.5°」もそのひとつで、竜の舌のような赤黒い能勢石(黒御影石)が55.5°の角度で南方上空に向かって突き出ていました。
この作品・・・この角度に意味があります。
春分と秋分の日の年2回、南中した太陽の高度とピタリと合わさり、作品の影がなくなるのです。1年に2回だけ無言で時を告げる日時計なのです。
地球と太陽の位置からくる自然のリズムと日本という場所に住む私たちの生活のリズムが、力のある作家のひらめきと技術によって芸術作品に凝集されています。
残念ながら作品は阪神大震災の頃に三宮からなくなりました。
山口先生も今は鬼籍の人です。
でも作品の記憶はいつまでも残像として残っています。
元町画廊には山口先生の作品が数点展示してあったと思います。
なお、その後「55.5度」は移転されていたことが分かりました。
今回何気に検索してみると、垂水区にあるベルデ名谷1番館南西側にあることがわかりました。
懐かしい人に出会った気分です。
以下のホームページで神戸の野外彫刻を紹介されている方がいます。
非常に労力のかかる作業だと思います。
http://www.rokko.gr.jp/~icchan2/7taru/7210.htm
Posted by alterna at
16:42
│Comments(0)
2007年07月13日
第七夜 元町のキューピットを捜せ

写真:元町のキューピット“ボス”
写真の彼は元町のキューピットです。名前をボスと言うようです。相棒の名は不明です。元町2丁目から3丁目辺りで出会うことがあります。
いつも会えるわけではありません。存在を知ってから2年ほどになりますが、運よくめぐり会えたのは4回くらいです。そんなもんで、キューピットたちに出あう日はラッキーな日と決めています。こういうことは思い込みが肝心です。
いつの頃からか2匹になったようです。

写真:ボスの相棒
とてもクールです。黙って街と人を眺めています。
無口です。呼びかけてもワンとも言ってくれません。
腹がすわっています。目の前を車が通ろうが、動じる気配もありません。
今日も街の平和のためにニラミをきかせてくれています。
キューピットたちを知ったのは元町3丁目にあるジャズのお店「ジャスト イン タイム」の磯田マスターのブログ「店主の呟き」を見てからです。マスターは「運がよければキューピット」というタイトルで書かれています。しかも元町を根城とするマスターをもってしてもやはり遭遇する率はきわめて低いようです。
ジャスト イン タイムは雰囲気のよい店です。月に数回レベルの高いジャズライブがあります。
いつもは数百万するスピーカー「パラゴン」が、分厚い音を響かせています。存在感十分です。磯田マスター曰く「80%くらいは能力を引き出せていると思う」。
このお店はマスターの感性の世界を具体的な形にしているのだなといつも思っています。漆喰のような白い壁とチョコレート色の柱との色彩バランスがとても落ち着いた雰囲気を醸しています。床も固くてベースの振動が一直線に伝わってきます。雰囲気、味、音などお店の構成要素すべてをスタンダード以上にしたいというコンセプトは見事に表現されています。
珈琲がお薦め! ココアはもっとお薦め!!
僕のお花のお師匠さんは、ここでココアをここ地よく楽しんでおられます。
店主の個性がよく反映されている店は良い店だと思っています。
チェーン店にはないオリジナルな個性が人の流れを変えています。
「運がよければキューピット」はhttp://sound.jp/justintime/tubuyaki4.html
ジャストインタイムのトップページはhttp://sound.jp/justintime/ です。
Posted by alterna at
15:25
│Comments(0)
2007年07月06日
第六夜 神戸ビエンナーレ2007

画像:「神戸ビエンナーレ2007」シンボルマーク
ビエンナーレというのは2年ごとにという意味です。「鼻炎になーれ???」という語呂で覚えている人もいます。
普通ビエンナーレというと現代アートの祭典を意味することが多いようです。3年ごとならトリエンナーレといいます。芸術展は企画に時間がかかりますし、お金も調達しないといけません。2年か3年ごとでないとなかなか開催が難しいところがあります。
ちなみに毎年やる場合はアニュアルといいます。新開地アートビレッジセンターでやっている現代アート展は「アートアニュアル」と言っています。
ビエンナーレはベネチアやサンパウロが有名です。しかし近年アジアの国々がビエンナーレを開催しています。アジア最大の光州ビエンナーレは大きな国家プロジェクトですし、1996年からの上海ビエンナーレに加えて、2006年にはシンガポールビエンナーレが開催されています。
日本でも福岡アジアトリエンナーレ、横浜トリエンナーレ、越後妻有アートトリエンナーレなどが良く知られています。
ビエンナーレ、現代アートといっても、恐れることはありません。要は芸術発表の場です。洋画や彫刻もかつては現代アートだったのです。
現代アートの作品は分かりにくいものが多いと思いますし、事実、自分に分かりにくいものはやはり多くの人にもチンプンカンプンなようです。「なんじゃこりゃ」と思うものは、やはり多くの人にも「なんじゃこりゃ」なのです。
でもその「なんじゃこりゃ」を制作する作家たちは、話してみるとなかなか面白い人が多いです。
自分の作品のここをわかってほしい
自分はこんな気持ちでこれをつくっている・・・などなど。
作家たちは理解しようとする気持ちをもっていると感じる人にはとても雄弁です。ましてや作品や作家の感性と共鳴するような感覚の人に出会ったら、これ以上幸せなことはないといった感じで、話してくれます。
今年、神戸でもビエンナーレが開催されます。「港」「出合い」「多様性」「街からの発信」「いろんなもの」などが要素になっているように思います。
メイン会場は港町神戸の象徴的な場所「メリケンパーク」です。表現の舞台はコンテナ・・・港から港へ「もの」「情報」「気持ち」を運び、物語を作ってきた「箱」です。モノを運ぶのにもっとも合理的に作られた、いわば規格品で個性のない「箱」をアーティストの発想の妙で個性的で多様な芸術空間に変えようという試みです。なかなかのアイデアだと思います。
神戸ビエンナーレを通じて多くの奇想天外に出会うことで、「なんじゃこりゃ」が「なるほど」「こんなやり方があるのか」に変わり、さらには日常のなかで「自分なりの工夫」や「自分流の楽しみ方」に発展していくことになると日々の生活に奥行きがでてくるでしょうし、アートに接することの面白さや大切さが一層実感されると思います。ましてや、会場で出会ったアーティストと人間的な付き合いなどに発展していくことがあれば、人生はより一層味のあるものになると思います。
10月6日から11月25日までの51日間、メリケンパークを中心にしながらも、街全体を会場にして大道芸、音楽、ファッション、ロボットメディア、スィーツデザインなど様々な創造的表現(アート)が展開されます(会場はそれぞれ確認してください)。
この多様さは神戸らしさの象徴でもあると思います。
是非、日頃なじみがあまりないアートの最前線を体験してください。
好奇心と馴れ馴れしさがあれば面白い経験になると思います。
詳細はこちらhttp://www.kobe-biennale.jp/まで
Posted by alterna at
17:49
│Comments(0)