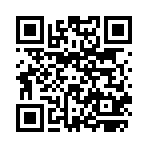2007年07月27日
第九夜 神戸の洋食屋さん

写真:伊藤グリル
神戸は明治の開港以来、みなとを軸に「ひと」「もの」「こと」に関する世界と日本の窓口となって「文化の翻訳と伝達」という歴史を築き上げてきました。ジャズ、映画、洋菓子、ゴルフ、コーヒ、パーマネント、洋家具など「神戸はじめ」と呼称される数々のものは、神戸がいちはやく世界の文化を取り入れ、全国に発信する街だったことの証しです。
実は「洋食屋さん」も神戸らしさを伝える街の魅力だと思っています。
鎖国が解かれた日本。富を求めて次々にやってくる欧米列強国の商人たち。
造船など新しい産業で賑わう街を支えた人たち・・・。
その活動を支え、疲れを癒す料理を提供したのは客船やホテルなどのコックたちでした。真摯に学び、外国人客の細かなオーダーに応じる過程で鍛えられ、そしてさらなる研究を重ねて味を探求したコックたちの、好奇心と職人気質が神戸洋食のルーツを形成していきます。
神戸洋食の系譜は、1882年に旧居留地に開業したオリエンタルホテルなどで修行し、独立していったコックたちの系統(その他のホテルの系統も含みます)。もうひとつは豪華客船で欧米と神戸を結んだ「日本郵船」で船旅を支えたコックたちが陸にあがって開いた洋食屋の系統。そしてもうひとつは、かつて「東の浅草、西の新開地」と呼ばれた文化の情報発信拠点だった街・新開地で生まれ東へ向かった洋食の系統です。

写真:左から ハナワグリル、グリル一平、帝武陣
神戸洋食の三つの系譜にルーツをもつコックたちが、港まち神戸で洋食屋として伝統のなかにも個性あるその店ならではの「味」を今日まで伝えています。それは「味」を毎日一から作るのではなく、伝統の「味」のベースやレシピを受け継ぎ、素材を継ぎ足し継ぎ足しすること、つまり元の味に近づけようとする模索のなかで独自の味が創られていったのです。神戸洋食の伝統の「味」はただ守られているのではありません。そこには常に創意と工夫が加えられ、「進化し続ける伝統の味」というべきものが、ノスタルジックな暖簾のむこうに、今日もその店のアラカルトなどを通して提供されています。
今、ご当地検定など、さまざまな分野で「らしさ」と言うものを再認識しようという試みがされています。神戸が街の個性を都市ブランドとして発信し、多くの方に神戸の魅力を知ってもらうためには、神戸「らしさ」を再認識する努力を怠ってはならないと思います。伝統と現代が融合された神戸洋食は神戸らしさの一角を担う都市ブランドのひとつだと思います。
ex:日本郵船系:伊藤グリル、ハイウエイ、明治屋神戸中央亭など
旧オリエンタルホテル系:クックナカタ、神戸開花亭、帝武陣など
その他ホテル系:神戸キチン、十字屋、ハナワグリル、もんなど
新開地発祥:赤ちゃん、グリル一平など
注:独断的分類ですので、詳しくはお店などで確認してください
Posted by alterna at
18:05
│Comments(0)