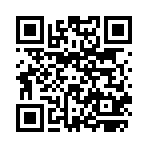2007年08月24日
第十三夜 今と昔を売る店(後編)

丹波の名物はさておき、城下町というのはまた骨董品のよく出る町でもあります。篠山も丹波焼(立杭焼)、王地山焼(篠山藩の御用窯)、三田焼(青磁や志手原焼などの陶器)の郷に近く、古丹波、三田青磁などがよく出ます。僕がよく行くお店に「庄次郎」さんがあります。ご主人は奥山さんという方ですが、「庄次郎」は何代か前の当主のお名前と伺いました。
「庄屋さんをされていたのでしょう」と自信を持って尋ねると「いいえ!」(ありゃ!)「江戸時代では藩御用達の魚屋で魚屋(ととや)庄次郎と称していました。代々庄次郎と庄兵衛を交互に襲名していたので、私の代は庄次郎。だから、お店も庄次郎ですわ」とのこと。とても紳士的で、また博識な方で、町の魅力アップに取り組まれるなどアイデアマンでもあります。
印象に残った庄次郎さんの言葉を紹介しておきます。
「篠山で3代に渡って同じ商売をしているところはほとんどない。蓄積された暖簾(ノウハウ)と資本をもとにしてその時代と折り合いをつけていかないとダメみたいです。店の前を行き来する人の嗜好がずっと一緒だと思っていると、店はつぶれます。」
永遠であるためには常に変わっていく必要がある、ということでしょうか。

写真:庄次郎さんのギャラリー
さて、城下町の景観に配慮して設計された「庄次郎」さんのお店は篠山城の堀の西側、御徒町の武家屋敷通りにあって、観光案内所兼骨董ギャラリー兼カフェになっています。僕は御徒町を読めませんでした。結構ポピュラーな言葉のようですが「おかちまち」と読むそうです。足軽よりは上のランクで鎧甲冑をつけることを許された歩兵のことだと伺いました。御徒町はそういう階級の武士たちの住居の集まったところで、たいがいの城下町にはあるようです。(たそがれ清兵衛のような世界をイメージしてください)。数十年前までご存命だった長老衆のなかには幕末に京都まで鎧兜をまとってはせ参じた経験がある方がいたようです(結局行ったけど時の情勢が決してしまっていて、そのまま帰って来られたようです。もし機転が利いた人がいてもっと早く行っていたら、生きて帰っていないかもしれません。生きながらえたその後の人生がどうであったかはともかく、こんな話にも「運」を感じます)。町の事を聞きながら、珈琲が飲めて、しかも時代を超えてきた骨董の品々も見られるというお店です。
骨董は同じものはまずありません。それとの出会いは一期一会という言葉がふさわしい瞬間です。迷った挙句に次の機会にと思って行っても、もう他人の手に渡っています。こういうときは縁がなかったと潔くあきらめるしかありません。

少し時代を感じる器に、今この季節しかない花などを一枝さしてみると、なんとなくほんわかした気持ちになります。オーラの泉で三輪昭広さんが「花は自分を見てくれる人に精一杯の美しさを提供して、その人を幸せにしてあげようとしている。だから部屋には花を飾りなさい」と言われてましたが、少しだけ分かるような気がします。

Posted by alterna at 19:10│Comments(0)