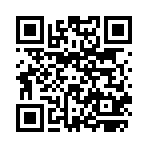2007年09月28日
第十八夜「ロダン・ロダン・ロダン(後編)」

神戸市中央区は旧葺合区と旧生田区が1980(昭和55)年に統合されてできた区です。
話の展開がシリアスからパロディへと急ですが、その旧葺合区、大安亭市場には「ロダンの狸」という彫刻があります。モデルは界隈の人たちが創った物語のなかの狸くんです。「ロダン」の創った「狸」ではなく「ロダンの狸」という作品名です。
淡路島に住んでいた芝居好きのタヌキが神戸の葺合、大安亭という芝居小屋で評判の役者に芝居で勝負を挑みますが、負けてしまいます。意気消沈しながらも、タヌキは一座とともに修行の旅に出て、数年後、大安亭で堂々の芝居をして捲土重来を果たします。
町の人たちは頑張ったタヌキを「ロダンの姿が素晴らしい」と褒めました。
この「ロダン」・・「魯之男子(ろのだんし)」が略されたもので、「物事をまねるのではなく、精神を学ぶ」という意味の中国の故事だそうです。大安亭市場の人たちは必死で修行して芸と心を磨き、立派な芝居をしたこのロダンのタヌキを「頑張りの神様」「大願成就の神様」としてその後も尊敬したということです。
(ふきあいの民話「大安亭ロダンの狸」より)
http://www.kobeyaku.org/chuyaku/omake/hkmnw.htm
ロダンの狸は大安亭市場の北側入り口に設置してあります。
ロダンの狸が創られていった過程がまた面白い。
葺合には和歌に詠まれた美しい町名、地名が残っています。また、芦屋から生田川辺りは明治のころまで、菟原(うばら)と呼ばれたところ、美しい娘と娘に恋をした二人の若者との悲恋の伝承を伝える処女塚(おとめづか)、東西の求女塚(もとめづか)などもあります。そんな地域の歴史を大切にしながら商店街の活性化を図ろうと、遊び心をもってみんなで考えていくうちに、新しい物語ができ、それがランドマークに繋がり、また、それにちなんだお店ごとの(一品ではなく)逸品も考え出されたりしていきました。主人公に狸を選んだのは、かつて大安亭市場に狸が住んでいたという言い伝えがあったからだとも伺いました。
僕が素晴らしいと思う点は
・ 話し合いの場ができたこと
・ 界隈の成り立ちの史実を横糸に、自分たちで考えた主人公の狸を縦糸にして、物語りを編んでいること
・ 誰もが楽しく見ることができるランドマークに物語を結晶させたこと
・ 物語を商店の逸品として商品化したものもあること
などです
現代に創られたこの物語も数十年もたてば、すっかり界隈に根付き、町の伝承として、語られていると思います。

写真:左「ロダンの狸」/右「商店街のタペストリー」
ふきあいの民話にはこのほか「こころやさしい天狗」「かすがの坂の気のいいナマズ」「五郎太の木」などがあり、地域のマンホールのデザインにも取り入れられています。

写真:左「かすがの坂の気のいいナマズ」/右「ナマズのデザインされたマンホール」
街の魅力は人の生活が積み重なったものです。そうであれば、今この時代の取り組みも、将来の神戸文化の地層のひとつになっていくものです。個性ある取り組みは、時代の指紋として自分たちが存在した証しを後の人たちに伝えてくれるはずです。
まちづくりの大切さはここにあるように思います。
たぶんロダンも自分の名(意味は違いましたが、ロダンの名前も意識されているように思います)と同じ狸が、遠く離れた極東の街で創られたことをほほえましく見ていると思います。

写真:ロダン「青銅時代」
場所は変わって、神戸市役所1階ロビーにもロダンの作品「青銅時代」があります。
こちらはまさしくロダン???
肉体の力強さと内に宿る精神性が緊張感をもって表現されています。
ロダンの「青銅時代」はあまりにリアルなことから、生身の人間で型をとったのではないかと疑惑をかけられた作品です。こんなロダンも国立美術学校の受験に3回も失敗し、入学をあきらめたということですから、わからないものです。
なお、神戸市役所1号館は彫刻の宝庫です。1階ロビーにはロダンのほかマイヨール、ブールデル(作品は建物の外で、市役所南西の角)といった世界的巨匠の3作品と柳原義達、佐藤忠良、船越保武といった日本の具象彫刻の巨匠の3作品が鎮座しています。これらすべて1号館ができたときに、多くの方の寄附金で設置されたものと伺いました。
ともかく、これでロダンが3つ・・・「ロダン・ロダン・ロダン」でした。
お後がよろしいようで!!!!!
Posted by alterna at
16:11
│Comments(0)